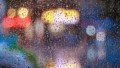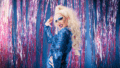第10話:最後の夜を迎える前に
彼から「会いたい」と連絡があったのは、金曜日の夜。
珍しく、彼のほうから誘ってきた。
私は仕事を早く切り上げ、少しだけ高めのリップを塗り直した。
馬鹿だなって思う。
それでも、彼の「今夜は君といたい」のひとことで、全部どうでもよくなってしまう自分がいる。
待ち合わせは、いつもの駅。
人通りの少ない改札口。
彼は、スーツ姿で立っていた。
シャツの第二ボタンまで外し、無造作にネクタイを緩めている。
いつも通りの、女を落とす仕様の彼。
でも今日は――どこか、違った。
「今日さ、君に会って話したかった」
彼がそんな風に切り出すなんて、初めてだった。
「話って?」
「うん……いや、ちょっと飲もうか」
居酒屋でも、バーでもなく、なぜか彼は静かなホテルのラウンジを選んだ。
グラスの氷が溶けていく音だけが、やけに響く。
彼は珍しく、グラスに口をつけなかった。
「なあ」
彼が視線を落としたまま言った。
「もし、俺が全部嘘ついてたとして……それでも、君は俺を好きでいてくれるの?」
一瞬、息が止まった。
なんの話?
全部って、なに?
「君だけじゃなかった。たぶん、これからも一人に決められない。
でもさ、どうしても君のことだけは、手放したくないんだ」
最悪の告白だった。
でも、最高に本音だった。
彼は、私のことを愛していない。
だけど、私という存在が“彼を肯定してくれる何か”として必要だった。
その歪んだ愛情が、
私の依存心とぴったり噛み合っていた。
「……私も同じだよ」
私は静かに言った。
「あなたがどれだけ最低でも、ずるくても、他の女を抱いてても、
私が欲しいのは“あなただけ”だから」
言葉を選べば、私はこの愛を断ち切れたかもしれない。
でも、選ばなかった。
私は彼を愛していた。
そしてたぶん、自分を一番安く扱うことでしか愛される術を知らなかった。
夜は深くなる。
この夜が、最後になるかもしれない。
でも、今はそれでいい。
終わりを知っていても、抱かれたい夜がある。
彼の腕の中で目を閉じながら、私は心のどこかで祈っていた。
――どうか、今日だけは私だけを見て。
第11話:愛していたのは、誰?
目が覚めたのは、午前4時過ぎだった。
隣には、彼がいた。
深い眠りの中。寝息すら穏やかで、罪の匂いなど微塵も感じさせない。
それなのに、なぜか涙が出た。
昨夜、あんなに求め合ったはずなのに。
肌を重ねて、心をさらけ出した気がしたのに。
それでも私の胸には、ぽっかりとした空洞だけが残っていた。
「好きだよ」
そう囁かれた夜は、これまでに何度もあった。
でも、心に響いたことは、一度もなかった。
彼が私を愛しているように見えたのは、
私が“愛されている自分”にしがみつきたかっただけだったのかもしれない。
スマホを開くと、彼からのメッセージが1件残っていた。
送信時刻は、私がシャワーを浴びていた頃。
「ごめん。今日は少しだけ、ちゃんとしようと思ってる」
誰に送ったのかは分からない。
でも、私じゃないことだけは確かだった。
“ちゃんとしよう”って、誰に対して?
私との関係を終わらせることを、誠意と呼ぶのなら、あまりに皮肉だ。
彼がうっすらと目を開けた。
「起きたの?」
「うん」
「そっか」
それだけの会話だった。
愛し合ったはずの夜の翌朝は、まるで他人同士のように淡々としていた。
私たちの関係は、いつからこんなふうに“消費”されるものになったんだろう。
愛し合っているつもりで、実は、ただの“互いの寂しさを埋め合う作業”をしていただけだったのかもしれない。
「ねえ……」
私は彼に背を向けたまま、小さく言った。
「もし、私がいなくなっても、平気?」
彼は黙った。
少しして、笑うように言った。
「それ、聞く?」
「うん。聞きたい」
「……平気だよ」
やっぱり。
そうだよね。
私は、何も残せなかったんだ。
私はベッドから降り、服を静かに身にまとった。
彼のほうはもう見なかった。
「じゃあね」
それが、彼に言った最後の言葉になった。