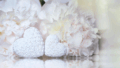プロローグ
街のネオンがぼんやりと揺れ、夏の夜風が窓の隙間から静かに部屋へと流れ込んでくる。
私はベッドの上に座り込み、スマートフォンの画面を何度も見つめていた。
指先が少し震えているのを感じる。
何度も何度も彼の名前が表示される通知を確認したけれど、新しいメッセージは届いていなかった。
「…また、連絡がない」
小さな声で呟くと、胸の奥がギュッと締めつけられるような痛みが走った。
彼からの返信がないと、なんだか自分が置いてきぼりにされたような気持ちになってしまう。
その夜、静かな部屋に響くのは時計の秒針の音だけだった。
スマホの画面を見つめながら、思わず涙が溢れた。
「私は何をしているんだろう…」
何度も何度も自問しながら、どうしても「付き合おう」という言葉が聞きたかった自分に気づいた。
第1章:はじまりは軽い気持ちから
悠也(ゆうや)とは大学のサークルで知り合った。
明るくて話しやすく、誰とでもすぐに仲良くなれるタイプ。
最初のころは、ただの友達の一人だった。
でも、いつの間にか彼の存在が大きくなっていった。
授業の合間にささいなことを話したり、サークルの後に一緒に帰ったり。
何気ない時間が心地よくて、私はどんどん彼に惹かれていった。
ある日、悠也から飲み会の誘いがあった。
「久しぶりにみんなで集まるんだけど、来ない?」
軽い声に、私は自然と「行く」と答えていた。
その飲み会は楽しかった。
彼の周りにはいつも人がいて、笑い声が絶えなかった。
だけど、ふたりきりになった瞬間、悠也は私の手をそっと握った。
「一緒に帰ろうか」
その言葉に心臓が跳ねた。
帰り道、静かな夜の街をふたりで歩きながら、彼はぽつりと言った。
「俺たち、なんとなくいい感じだよな」
私は頷きながらも、何かが違う気がしていた。
付き合うという言葉はなかった。
それでも、彼といる時間は幸せだった。
自然体でいられる相手ができたと思った。
でも、それが始まりであり、曖昧な関係の始まりでもあった。
第2章:曖昧な関係の中で
悠也は会えば優しくて、まるで恋人のように接してくれた。
時には手を繋ぎ、時には肩を寄せ合い、甘い言葉もくれた。
「好きだよ」
その一言が、私の心を溶かした。
でも、その言葉の裏にあるものが、いつもぼんやりとしていて掴めなかった。
彼は決して「付き合おう」とは言わない。
連絡はいつも私からで、彼のほうからはあまり連絡が来なかった。
それでも、会えば必ず私のことを大切に扱ってくれた。
友達に相談しても、答えは冷たかった。
「それって、セフレだよ」
その言葉に傷つきながらも、彼との時間が幸せだった私は簡単に割り切れなかった。
私の中では、彼が本当に好きで、愛されていると信じていたからだ。
でも、心のどこかで気づいていた。
「これでいいのかな?」
彼の曖昧な優しさにすがりつく自分。
それが徐々に私を苦しめていった。