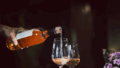職場でのその視線に、気づいていなかったわけじゃない。
「今日もお疲れさまでした」
「お昼、まだならこれ。僕の手作りです」
差し入れのおにぎり、帰り際の言葉、真っ直ぐすぎる眼差し。
彼――佐久間は27歳。私より6歳年下の、まっすぐで、素直で、でもちょっと不器用な子。
新人研修の担当になってから、もうすぐ1年。
仕事も覚えてきて、頼りがいも出てきた。
けど、まさか、こんな展開になるなんて。
「先輩、少しだけ、お時間もらえませんか」
金曜の夜。誰もいなくなったオフィスでそう言われた時、
心臓がひとつ跳ねた音がした。
「この後…よかったら一緒に飲みませんか?」
連れて行かれたのは、まさかの「Noir」だった。
彼が、私が通っているこのバーを知っているなんて。
「前に話してたから。来てみたくて…」
彼の照れた顔に、思わず笑ってしまう。
「こんばんは」
マスターが目配せをくれた。
何も聞かずに出してくれたのは、ピノ・ノワール。
しっとりとした赤、スミレとチェリーの香りが優しく包み込むような一本。
「ずっと…先輩のこと、好きでした」
その言葉は、ワインよりずっと早く、私の体を熱くした。
「初めて会ったときから、誰よりもかっこよくて、優しくて、強くて…でもたまにちょっと弱くて。
そんな先輩がずっと忘れられませんでした」
私は言葉に詰まった。
彼の想いがまっすぐすぎて、まぶしくて、そして少しだけ、罪悪感に似た感情が胸に広がる。
私が年上だから?
彼が若いから?
それとも、まだ“自信”がないだけ?
「ごめんね、すぐには答えられない」
そう伝えると、彼は優しく笑った。
「大丈夫です。今すぐじゃなくていい。
でも、先輩がどんなにかっこ悪くても、泣いてても、僕はちゃんと見ていたい」
その一言が、グラスの中のピノ・ノワールみたいに、
静かに染み込んできた。
ワインって面白い。
強くはないのに、そっと寄り添ってくれる。
ピノ・ノワールみたいな人に、今まで出会ったこと、なかったかもしれない。
帰り際、彼がマスターにお礼を言っていた。
「いいお店ですね。すごく落ち着きます」
その背中を見て、私はふと、思った。
恋って、“年齢”とか“立場”じゃなくて、
こういう優しさに、ふいに心をほどかれるものなのかもしれない。
ワインを飲んで泣く夜もある。
でも今日の私は、泣かなかった。
それはきっと、ピノ・ノワールのせいじゃなく、
彼の声とまなざしが、心にそっと灯りをともしてくれたから。